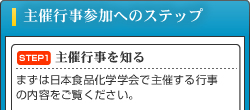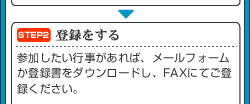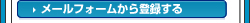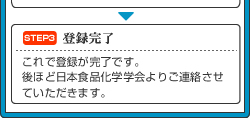1 会則第9条3項に基づき、学会誌へ投稿する者の筆頭著者並びに責任著者は学会員
(個人会員及び法人会員を所属名とする者)である必要があります。ただし、委員会
が依頼した原稿は除きます。
責任著者(Corresponding author)は、連絡者として「投稿原稿の表紙」(以下表紙と
いう)を記載し、論文の代表者として、研究が日本食品化学学会倫理規定に従って行わ
れていることを確約する署名を行います。責任著者は、和文論文の場合、論文1ページ
目の欄外に、責任著者(連絡先)として日本語で、Corresponding author として英語で、
住所と氏名が記載されます。英語論文の場合には、1ページ目に Corresponding author
として英語で、和文抄録のページに、責任著者(連絡先)として日本語で、住所と氏名
が記載されます。
なお、論文が複数のグループで行われている場合を鑑み、責任著者は、2名まで認めま
すが、その場合どちらかが、連絡者兼代表者として表紙を記載し代表者署名を行って下
さい。
2 会誌への投稿は有料とします。ただし委員会が依頼した原稿は除きます。なお、受付の
順番を待たず、直近発行の学会誌掲載を希望される場合は、別途その実費を支払ってい
ただきます。
3 原稿の種類は下記に示す通りです。論文およびノートは、他の出版物に既に発表、ある
いは投稿されていないものに限ります。刷り上がりは本文和文で1ページ2段組みで
26 字× 51 行となります。従って1ページ当たり最大 2652 文字となります。
1) 総説(Review):調査・研究論文の総括、解説等。編集委員会が依頼する場合もあ
ります。
2) 論文(Regular article):科学的研究・調査の報告。
3) ノート(Note):研究の概略を迅速に発表、または部分的調査・研究の発表。
4) 資料(Research letter):調査または統計等をまとめた報告(その結果を十分に論
じたものは総説、論文とします)。学会員に参考となる記録やまとめ、学会員に役
立つ行政、判例あるいは海外資料。委員会が提供する場合もあります。内容によっ
ては投稿料を求めません。
5) 会員の意見:食品化学に関する意見、掲載論文に関する意見等。原則として投稿料
を求めません。
6) その他:編集委員会にご相談下さい。
4 投稿原稿執筆にあたっては、とくに形式を定めません。要は読み易く、文献として理解
しやすい様式および記述でお願いします。ただし、論文のタイトルは、分かり易いもの
とし、原則として副題は付けないで下さい。また、引用文献の記述には注意して下さい。
(Ⅱ-3)引用文献参照)
5 論文の投稿は、和文でも英文でも構いません。図表も同様です。投稿原稿には英文抄録
を原稿として付して下さい。また、英文論文の場合は、英文抄録の和文も別途添付して
下さい。抄録は、一般学術雑誌の例で作成されて構いません。しかし本誌では英文投稿
の場合、和文で会員が目を通すのに十分容易なように、また和文投稿ながら外国から文
献請求があると予想される英文抄録の場合、これら抄録はより詳しく本文の主要図表も
引用し、1~2頁分を使用しても構いません。
6 和文論文への英文抄録には、日本語訳を付けて下さい。ただし訳文の掲載は致しません。
7 投稿原稿には別に示す表紙(A4版縦)に所定事項を記入・署名の上、PDFにしてEMに
アップロードしてください。表題や連絡先など、記載内容に変更が生じた際も、その
都度に修正したものをアップロードしてください。
8 掲載に際し、軽微な修正は委員会の判断にご一任下さい。もし投稿原稿の意を害した場
合、その旨を寄せていただければ次号に掲載します。
9 注意:二重投稿などの不正が疑われた場合には日本食品化学学会誌倫理調査委員会規則
に則った調査が行なわれ、その結果に基づき日本食品化学学会倫理規定に従う処分がな
されることがあります。


(2023年7月改定)
日本食品化学学会誌(Japanese Journal of Food Chemistry and Safety、略名:日食化誌)以下"学会誌"は、学会員の食品に関連関与する化学物質の化学、安全、有用性、法律、経済、社会、歴史、行政、統計などに関する研究・調査結果を掲載することを目的とする学術論文誌であります。学会誌は、総説、論文、ノート、資料などの他、学会連絡事項等を掲載します。投稿および審査は全てオンライン投稿審査システム Editorial Manager®(以下EMという)で行い、学会員の投稿原稿は複数の査読者の意見を基に編集委員が評価し、その採否等は編集委員会(以下、委員会)が行います。
学会誌には食品添加物、残留農薬あるいは食品汚染物の調査データであっても学術的価値のあるものは論文として掲載します。ただし、その際、調査数が少なかったり、系統だった調査が行われていない場合には返却またはノート扱いとする場合があります。また、動物実験のネガティブデータも掲載しますが、投与量や実験方法等が不適当なものはお断りする場合があります。
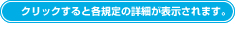
1 原稿の記し方と構成
1)緒言、研究方法、結果など見出しの項にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ...の番号を付して下さい。
以下の番号には通例 1、2、3 ...、1)、2)、3) ...、(1)、(2)、(3) ...として下さい。
2)文献記述は次のことを守って下さい。全文献共、同一形式( Ⅱ-3)引用文献参照)
に従って、原則として英文記載として下さい。
3)キーワードは和文、英文の両方で5句以内にお願いします。
2 表および図
1)原稿本文中に表、図および画像を挿入する記述箇所、右横に挿入箇所を朱色で明
示して下さい。
2)図と画像のタイトルは図および画像の下とします。表のタイトルは表の上としま
す。なお、図表の下側に本文と併読しなくても理解できる程度に簡単な説明文が
記述されていることが望ましいとします。
3 引用文献
1)引用文献は 1)、2) で出現順に示し、最後に一括して番号順に列記する。ibid.や
idem は用いない。
2)欧文誌の引用:例①のとおりとする。雑誌名は略記名の定められているもの以
外略さない。略記名が不明の場合は、略記せず完全誌名を記述する。
例① Viberg, H., Fredriksson, A., Eriksson, P.:Neonatal exposure to
polybrominated diphenyl ether (PBDE 153) disrupts spontaneous
behaviour, impairs learning and memory, and decreases hippocampal
cholinergic receptors in adult mice. Toxicol. Appl. Pharmacol.,
192, 95-106 (2003).
3)和文誌の引用:誌名は原則としてヘボン式ローマ字書きで記述し、欧文誌名を持
つものは、必要があれば丸括弧書きで付記する。正式な欧文誌名のないものは欧
文誌名を付けてはならない。また、欧文誌名は、その略記名が定められていると
きは略記しても良いが、略記名が不明の場合は略記せず完全誌名を記述する。
例②を参考にする。なお、英文標題がないものは標題をローマ字書きし、ローマ
字のあとに丸括弧に入れて翻訳標題を付記する。
例② Yoshimitsu, M., Hori, S.:Comparison of the DNA extraction methods
from potato snacks and detection of genetically modified potato in
snacks. Nippon Shokuhin Kagaku Gakkaishi (Jpn. J. Food Chem.), 10,
165-170 (2003).
4)欧文誌、和文誌とも、巻数を表記しない雑誌では、巻数の位置に年号を太文字で
記載する。
5)オンラインジャーナルの場合、ページ付けがある場合には、2)-4) に従う。
ページ付けが無く論文番号がある場合には、巻号を記載し、その後に論文番号を
記載する。
例③ Mabon, S. A., Misteli, T.:Differential recruitment of pre-mRNA
splicing factors to alternatively spliced transcripts in vivo.
PLoS Biol., 3(11), e374 (2005).
6)オンラインで事前公開された論文等で、まだ巻号、ページ、論文番号等が決定し
ていない場合、あるいはこれらのものがない場合には、分かっている情報を記載
し、その後にDOIを記載し、引用日について括弧書きで追記する。
例④ Xiao, B., Huang, X., Wang, Q., Wu, Y.,:Beta-asarone alleviates
myocardial ischemia-reperfusion injury by inhibiting inflammatory
response and NLRP3 inflammasome mediated pyroptosis. Biol., Pharm.
Bull., Article ID: b19-00926, doi:10.1248/bpb.b19-00926 (cited 2020-04-28).
7)欧文単行本の引用:図書の一章又は一部分を引用する場合は例⑤、⑥、全体を引
用する場合は例⑦を参考にする。ISBNが判明しているものは記載する。
例⑤ Porter, L. J., "The Flavonoids: Advances in research since 1986",
Harborne, J. B. ed., London, Chapman & Hall, 1994, p. 23-53.
(ISBN 0-412-48070-0)
例⑥ Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 55th Session ed.,
"Compendium of food additive specifications, Addendum 8", Rome, FAO,
2000, p. 49-50. (ISBN 92-5-104508-9)
例⑦ Watson, C. ed., "Official and standardized methods of analysis",
3rd Ed., London, The Royal Society of Chemistry, 1995.
8)和文単行本の引用:和文単行本を引用する場合、書名は原則としてヘボン式ロー
マ字書きで記述し、欧文書名を記す必要があれば翻訳し、ローマ字書きのあとに
丸括弧に入れて付記する。翻訳本を引用する場合には、必ず著者及び原書名を記
述し、翻訳者と翻訳書名を丸括弧に入れて付記する。図書の一章又は一部分を引
用する場合は例⑧~⑫、全体を引用する場合は例⑬~⑮を参考にする。ISBNが判
明しているものは記載する。ただし、和文原稿において、団体著者、団体編者の
場合や、書名がローマ字書きをすると意味がわかりにくくなるものは、和文で記
載してもよい。例⑯〜⑱を参考にする。
例⑧ Shigematsu, Y., "Saishin No Masusupekutorometori (Modern mass
spectrometry)", Niwa, T. ed., Kyoto, Kagaku Dojin, 1995, p. 80-92.
(ISBN 4-7598-0282-7)
例⑨ Suzuki, I. et al. eds., "Shokuhin Tenkabutsu Koteisho Kaisetsusho,
7th Ed.", Tokyo, Hirokawa Shoten, 1999, D-661 D-667.
(ISBN 4-567-01852-4)
例⑩ Ono, H. et al. eds., "Shokuhin Anzensei Jiten", 1st Ed., Tokyo,
Kyoritsu Shuppan, 1998, p. 246.
(ISBN 320-06124-1)
例⑪ Kudo, I., Inoue, K., "Purosutaguranjin Kenkyuho, Jo-kan (Technique
for the study of prostaglandin, volume 1)", Yamamoto, S., Katori,
M. eds., Tokyo, Tokyo Kagaku Dojin, 1986, p. 47-53.
(ISBN 4-8079-1305-0)
例⑫ Derome, A. E. (Takeuchi, Y., Nosaka, A. trs.), "Modern NMR techniques
for chemical research(Kagakusha No Tameno Saishin NMR Gaisetsu)",
Kyoto, Kagaku Dojin, 1991, p. 185. (ISBN 4-7598-0226-6)
例⑬ Ito, Y. ed. (Division of Food Chemistry, Environmental Health Bureau,
Ministry of Health and Welfare, Japan supervised), "Nipponjin No
Shokuhintenkabutsu 1-Nichi Sesshuryo Jittai Chosa Kenkyu (Studies on
daily intake of food additives in Japanese 1976-1985)", Tokyo, Shakai
Hoken Shuppansha, 1988.
例⑭ Niwa, T. ed., "Saishin No Masusupekutorometori (Modern mass
spectrometry)", Kyoto, Kagaku Dojin, 1995. (ISBN 4-7598-0282-7)
例⑮ Murota, S. ed., "Purosutaguranjin No Seikagaku (Biochemistry of
prostaglandins)", 1st Ed., Tokyo, Tokyo Kagaku Dojin, 1982.
例⑯ 厚生省生活衛生局食品化学課"第2版 食品中の食品添加物分析法"2000,
p. 320-322.
例⑰ 農業環境保全対策研究会編"残留農薬基準ハンドブック-作物・水質残留の
分析法-"東京、化学工業日報社、1995, p. 406-410.
例⑱ 動物性食品のHACCP研究班編(厚生省生活衛生局乳肉衛生課監修)
"HACCP: 衛生管理計画の作成と実践データ編"東京、中央法規出版、
1997, p. 148-152.
9)官報、局長通知など和文原稿では例⑲、 ⑳に従い引用する(英文にしない)。
英文原稿では、例㉑〜㉓を参考に引用する。
例⑲ 厚生省令第50号 (1995)"既存添加物名簿に関する省令"平成7年8月10日。
例⑳ 厚生省生活衛生局長通知"食品衛生法に基づく表示について"平成7年10月
12日、衛食第186号 (1995).
例㉑ Japan's Specifications and Standards for Food Additives, 7th Ed.,
Ministry of Health and Welfare, Japan (1999).
例㉒ Ordinance No. 50 (Aug. 10, 1995), Ministry of Health and Welfare, Japan.
例㉓ Notification No. 186 (Oct. 12, 1995), Director-General of
Environmental Health Bureau, Ministry of Health and Welfare, Japan.
10)和文誌及び研究所報告のローマ字書きと欧文名(丸括弧内)の例を下記に示す。
分析化学:Bunseki Kagaku(なし)
栄養学雑誌:Eiyogaku Zasshi (The Japanese Journal of Nutrition)
医学と生物学:Igaku To Seibutsugaku (Medicine and Biology)
医学のあゆみ:Igaku No Ayumi (Journal of Clinical and Experimental Medicine)
化学と工業:Kagaku To Kogyo (Chemistry and Chemical Industry)
化学:Kagaku (Chemistry), (Kyoto) 化学(Kyoto)と科学(Tokyo)を区別するた
め所在地を記入
日本農芸化学会誌:Nippon Nogeikagaku Kaishi(なし)
応用薬理:Oyo Yakuri (Pharmacometrics)
生化学:Seikagaku(なし)
食品衛生研究:Shokuhin Eisei Kenkyu (Food Sanitation Research)
薬学雑誌:Yakugaku Zasshi (Journal of the Pharmaceutical Society of Japan)
国立医薬品食品衛生研究所報告:Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho
Hokoku (Bulletin of National Institute of Health Sciences)
日本醤油研究所雑誌:Nippon Shoyu Kenkyusho Zasshi (Journal of the Japan Soy
Sauce Research Institute)
埼玉県衛生研究所報:Saitamaken Eiseikenkyusho Ho (Annual Report of Saitama
Institute of Public Health)
11)私信、講演要旨集(一般講演、シンポジウムなどを含む)、インターネットホ
ームページ、未発表のものは文献として引用しない。ただし脚注に記載するこ
とは妨げない。
12)脚注は *1、*2、*3 により表し、出現したページの下部に番号順に列記する。
4 その他の留意事項
1)簡単な化合物名や動植物名は、文部省学術用語審議会編 学術用語集によります
。用語集に記載のないものについては、広く学術的に用いられている用語を用
いて下さい。ただし、字数の多い化学名、酵素名、外国地名、外国人名、およ
び学術的に欧文の方が理解を得やすい場合は欧文で記載して下さい。
2)動植物名:片仮名書きとし、学名はイタリック体とします。ただし食品として
用いる場合はこの限りでありませんが、動植物、食品名などを学名によらず英
語名で図表などで一覧表としてデータと共に示す場合は必ず日本名を( )で
併記して下さい。
3)その他ゴシック体(太い文字)、イタリック体(斜体)および学名などスモー
ルキャピタルを必要とする場合は、その文字の下に朱書きでそれぞれ
、 および を記入して下さい。
4)J-stageに掲載の都合上、外字フォントは使用できません。
5)投稿原稿には、ページ番号に加え行番号を記載する。
6)投稿規程全般について不明な点、特殊な要望のある場合は学会事務局にお問い
合わせ下さい。
5 投稿の際の注意
1)ヒトを対象にした研究論文は、ヘルシンキ宣言(2008 年改訂) の方針に沿い、
必要な手続きを踏まえていなければならない。特に臨床サンプルを扱う場合に
は、原則的に所属機関の倫理委員会などの公的審査会にて認められた研究内容
で、同意書等を取得した上で得たデータでなくてはならない。
2)動物を対象にした研究論文は、所属機関で規程される実験動物に関する管理と
使用に関するガイドラインに従った旨を明記する。
1 投稿はオンライン投稿審査システムEditorial Manager®(EM)にて、システムの指示
に従い責任著者が行って下さい。責任著者はEMのサイトにてユーザ登録のうえ、アカ
ウントを作成する必要があります。原稿はWord、PowerPoint、pdfなどの一般的なファ
イル形式でアップロードできますが、本文テキストはWordで提出してください。
オンライン投稿審査システム
Editorial Manager® URL:https://www.editorialmanager.com/jjfcs/
問い合わせ:日本食品化学学会編集委員会
TEL / FAX:03-5498-5765 E-mail:jpnjfcs@gmail.com
2 受理決定後、出版のために印刷業者から著者校正ゲラが送られますので、確認し校正
作業をおこなってください。また軽微な修正や誤植などを編集委員会から指示するこ
とがありますので、その際は指示に従ってください。
1 校正は初校、必要あれば二校を著者が行います。ただし校正時の加筆はご遠慮下さい。
2 掲載された論文については、下に定めた諸経費を請求します。
1)基準投稿料:1編につき個人会員 20,000円、法人会員および企業 40,000円
2)規定頁(5頁)を超過した場合は超過費を請求します。
超過費用( 6,000円/1頁)は、19巻1号掲載分より実施しています。
3)カラー頁がある場合は実費を請求します。
4)トレース:実費を請求します。
5)別刷:実費を請求します。
6)pdf作成:基本作成費 1,000円+1頁あたり 1,000円
7)上記費用は投稿原稿掲載通知後、明細書により請求します。
3 掲載料の納入は原則として郵便振替をご利用下さい。(別刷代を除く)
郵便振替納入先:口座 00900-3-233186
加入者名 日本食品化学学会
(通信欄に送金内容を記入してください)
1 本誌に掲載された論文の著作権は、日本食品化学学会に属します。受理決定後は著作権
譲渡書に必要事項を記入・署名の上、提出してください。
編集委員会事務局の移動について(2025年1月)
オンライン投稿開始のお知らせ
➤オンライン投稿・査読システム Editorial Manager® ⇐投稿はこちらから!
投稿規定
投稿原稿の表紙
日本食品化学学会誌倫理調査委員会規則
編集委員一覧